
依頼者にとって最も良い解決は何か、
を常に考えながらサポートします。


身体を動かす刺激や振動が帯状疱疹の痛覚過敏を引き起こすので、動かないで横になっている時が一番楽である。横になって本を読むこともあるが、iPadでYouTubeの落語を聞く機会も多い。落語をたっぷり聞いてみたいという願いが帯状疱疹によって実現したのであるから皮肉である。
落語家のランキングのトップは、私の場合、ダントツで古今亭志ん朝である。言葉が明瞭であること、話の流れとテンポが良いこと、登場人物の声色や仕草が巧いこと、どれを取っても群を抜く。
トップに立川談志を挙げる人もいるが、私は好きではない。「落語は業の肯定」と定義しつつ、自分の巧さを鼻に掛けているところが鼻につくからである。志ん朝の落語は「業の肯定」そのままである。
志ん朝の落語の演目の一つに「三年目」というものがある。男女を問わず亡くなる人の髪を剃って坊さんのようにすることが極楽に行く近道との因習が残っていた江戸時代の話である。
結婚して2年で不治の病となった大店の若妻・お菊を主人は献身的に介護するが、病はさらに篤くなり、医師から最期の別れの機会を持つように告げられる。聞き耳を立ててそれを知ったお菊は絶望し、薬を飲まなくなる。必死に薬を飲ませようとする主人と、それに抵抗する会話の中で、気に病んでいることがお菊にあると判明する。もしやそれが回復しない原因かもしれないと、主人は告白を求める。遂にお菊もそれを口にする。
「私が目をつぶれば、貴方は間もなく次の奥様をもらい、その奥様を私にしてくれたように可愛がるに違いない。そのことを思うと恨めしくて・・・」
予想もしない回答に驚くと同時に腹を立てた主人は、「何をバカな」「私にとって女はお前一人だ」「お前が目をつぶった時は、後添えなどもらうことはなく、一生独り身を通す」と反論する。しかしお菊は納得しない。「これだけの身上を持ち、まだ若い貴方を、御両親や親戚が独り身のまま置いておくはずがない。説得され、いずれは再婚することになる。そうなれば、私にしてくれたように・・・」と引き下がらない。
困った主人が最後に持ち出した案が「どうしても再婚しなければならなくなったら、婚礼の夜、幽霊になって出ればよい。驚いた新妻はすぐに実家に戻り、亡妻の幽霊が出るという噂が広がれば、嫁に来る人はいなくなる」というものであり、「幽霊であっても私はお前に会いたい」と付け加える。結局、お菊との間でそのような約束が成立し、ほどなくお菊は亡くなる。
お菊が予想したように、百箇日を迎える頃には周りからの再婚のプレッシャーが激しくなるが、主人はプレッシャーに抵抗し、再婚を拒む。しかし、大店の経営者という立場と世間体に押され、結局、多くの後妻希望者(この主人イケメン)の中から選ばれた女性との間で祝言を挙げる。
その夜、八つ(午前2時)の鐘と同時に幽霊として出るというお菊との約束が実行されると信じている主人は、お床入りを拒んでまんじりともせず八つの鐘を待つが、お菊の幽霊は出なかった。はるかに離れた西方の浄土から来るのだから、初日に間に合わないこともあるかもしれないと、次の日もお床入りせずに八つの鐘を待つが、結局お菊の幽霊は出ないまま1ヶ月が経過した。
そうなると主人の考えにも変化が生じてくる。
「(幽霊になって出るというのは)生きている時の約束で、死んでしまえば関係ないのではないか」「あの世で楽しくしているのではないか」
ほどなく新妻との睦まじい生活が始まり、玉のような男の子を授かることになった。
そしてお菊が亡くなって三年目の亡妻の法要の日、3人でお墓参りをし、浅草で食事をして、早めに眠りについたこともあって、夜中に目を覚ました主人は、緑の髪を振り乱したお菊の幽霊を見ることになる。主人の約束違反を「恨めしい」と詰るお菊に対し、「なぜ祝言の夜に出なかったのか。今頃になって出たお前の方こそ約束違反だ」と主人は強く反論する。
これに対し、お菊は次のように答え、落ちとなる。
「だって貴方、お墓に入れる時、みんなで私の髪を剃ったでしょう。そのままで出たのでは貴方に嫌われるので、髪の毛が伸びるまで(3年間)待っていた」
この演目に入る前に、志ん朝は枕として自分のエピソードを紹介している。財布を忘れたことを知らずに近所の喫茶店に入ってコーヒーを飲んでいたところに、1万円を立て替えてもらった人が偶然入ってきた。コーヒー代だけであればツケにできるが、1万円まで喫茶店から借りる訳にはいかず、喫茶店から自宅の妻に電話を入れ、すぐに財布を持って喫茶店に来るように指示する。
「そんなことは後でも・・・」と言って帰ろうとする1万円を立て替えてくれた人を「間もなく来ますから」と引き留めて、30分して喫茶店に来た妻を見たら、スカートにブラウス姿で薄化粧までしていた。「一刻も早く財布を持ってくるように指示したのだから、いつもの上下のトレーナーのまま突っ掛けで走ってくるべきなのに・・・」と志ん朝は呆れる。
この枕からすると、お菊のこの答えは、女性というものはつまらないことにこだわることが多いという例と位置付けられる。
「三年目」を取り上げたのは、最近読んだキャロル・ギリガンの「もうひとつの声で」(風行社)を読んだからである。この本は「ケアの倫理」の古典、増補版新訳である。十六の言語に翻訳され、フェミニズム研究の金字塔として読み継がれている。
ケアの倫理は、人間を自律した個人ではなく関係の網目の中にある存在ととらえる。
この本の中に、一人は男子、一人は女子のともに11才の子供の道徳判断の違いが分かる設問が出てくる。
ハインツという名の男が、金銭的に手の届かない薬を、妻の命を救うために盗むべきか否かを考えているという場面を取り上げ、ハインツの窮状、妻の病、そして薬剤師による値下げの拒否という、ジレンマを説明した後、「ハインツは薬を盗むべきか」という質問を二人に投げかける。
男子は、ハインツは薬を盗むべきだ、という意見を最初からはっきりと持っていた。所有の価値と生命の価値との衝突の問題であると整理した上で、論理的に考えて生命の方が優先されるべきだと考え、その根拠として、人間の命はお金よりも価値があることを挙げている。もしハインツが妻を愛していないとしても薬を盗むべきかと尋ねられると、それでも盗むべきだと答える。「嫌うことと殺すことは違う」だけでなく、もしハインツが捕まったとしても「裁判官もきっと、ハインツは正しいことをしたと考えると思う」からだと言う。ハインツが薬を盗めば、法律を犯すことになるという点について尋ねられると、「法律にだって間違いはあります。それに、想像できるすべての場面に対する法律を書き上げることなんて不可能です」と答える。
男子は状況を正しく整理したうえで抽象化し、法律を前提に合理的な結論を出す。彼にとってジレンマは「数学の問題のようなもの」だ。従来の心理学に従うなら、論理的な思考に長けた、自律した少年と見なされるだろう。
一方女子の答えは釈然としない。お金を借りるとか、盗む以外の方法もあるのではないか?盗んだらハインツは牢屋に行くことになり、妻はもっと病気が悪くなるのではないか?11才の女子は自分もその状況に巻き込まれたかのように逡巡し、妻の思いや、薬剤師のニーズにも応えようとする。このジレンマの解決策として、人とのつながりを断ち切るのではなく、コミュニケーションを通してネットワークを活発化させて、むしろそのつながりを強めることで、ハインツの妻がネットワークから排除されないようする、という考えを示している。
「自分自身への責任と他者への責任が衝突する場合、人はどのようにして選択をすべきだと思いますか?」という問いにこの女子は以下のように答えている。
「私は仕事なんて、夫とか両親とか本当に近しい友人とか、自分が本当に愛している人に比べれば重要ではないと思っています。」
「自分が本当に大切に思っている人、自分が本当に愛している人で、自分自身のことと同じレベルかそれ以上に愛している相手だったら、自分が真により深く愛しているものは何か、という問いへの答えを出すしかありません。その人なのか、そのものなのか、あるいは自分自身なのか。」
「三年目」のお菊にとって、主人が今でも自分を愛してくれていること以上に重要なことはない。再婚した新妻に対抗する意味でも、坊主のような頭で出て行く訳にはいかないのである。関係性の網目の中にいるお菊にとっては、再婚相手との祝言の日に出るという夫との約束よりも、髪の毛が伸びるのを待ち、主人に嫌われないようにすることの方が重要である。
お菊の行動をもって「つまらないことにこだわる」と見るのは間違っているのではないか。人間関係の網目の中にいれば、そのように判断する方が通常ではないか。
平野啓一郎は「私とは何か-「個人」から「分人」へ 」(講談社現代新書)の中で、
「たった一つの「本当の自分」など存在しない。裏返して言うならば、対人関係ごとに見せる複数の顔が、すべて「本当の自分」である。」
と説く。つまり、
「人間は決して唯一無二の「(分割不可能な)個人 individual」ではない。複数の「(分割可能な)分人 dividual」である。分人はすべて、「本当の自分」である。」
「私たちは、しかし、そう考えることが出来ず、唯一無二の「本当の自分」という幻想に捕らわれてきたせいで、非常に多くの苦しみとプレッシャーを受けてきた。」
「どこにも実体がないにも拘わらず、それを知り、それを探さなければならないと四六時中嗾されている。」
とも説く。
平野啓一郎は愛について「「その人といるときの自分の分人が好き」という状態」つまり「他者を経由した自己肯定の状態」が愛であるという。他者を経由した自己肯定が愛であるとすれば、「三年目」のお菊にとって、唯一の他者である夫の目に映る自分の姿は、愛を左右する極めて重要な要素である。
「環境が変われば、当然、分人の構成比率も変化する。」
夫は新しい妻や子供という、その後生じた分人が加わり、お菊との関係(分人)は想い出の中に出てくる程度に低下したが、お菊にとっては唯一の人間関係である。
「分人というのは、他者が存在しなければ、発生もしないし、維持も出来ない。たえず相手とのコミュニケーションを通じて更新され続け、鮮度を保ち続けている。」
死亡し、夫との更新がストップし、亡くなった時のことのみを記憶しているお菊の立場からすれば、3年目に出る必然性があるが、他の分人(新妻や子供)との更新を続けている夫にとっては「今さら何を」ということになる。
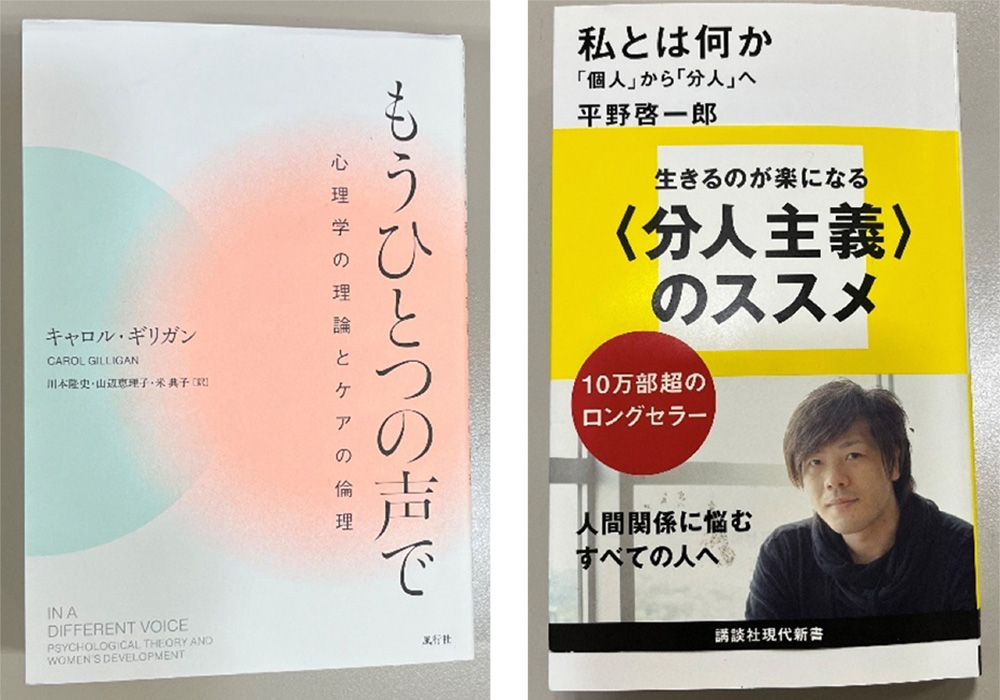
「分人全体のバランスが重要」と平野啓一郎は説くが、バランスを拒否し、一人の分人との関係のみに注目し、その人との関係で生じたモヤモヤの解消をトコトン求めるケースは珍しくない。お菊が毎晩幽霊として出れば、ストーカーである。気に入ったホストが喜ぶことのみに傾倒し、借金をしてホストクラブに通い、経済破綻した例などもバランスを欠いた例である。
それらは極端な例だが、一方で、三年目に幽霊が出た時の夫の反論や、「ケアの倫理」の11才の男子の選択の方が筋道が立っているように見えるのは、「もうひとつの声で」の著者のキャロル・ギリガンによれば、人間の発達を男子をモデルにして考えてきたからであり、成熟の基準が偏っていると主張する。
著者は男子の子供のような道徳性を「正義の倫理」、女子のような道徳性を「ケアの倫理」と名づける。
人間を自律した個人ではなく関係の網目の中にある存在ととらえる「ケアの倫理」の方が「分人主義」にも合致する。「正義の倫理」に慣らされている私達男性は、お菊の訴えをつまらないこだわりと排斥しがちだが、お菊の訴えの方が普通である。「ケアの倫理」は「正義の倫理」の一面性を補完・補充している。
「正義の倫理」と「ケアの倫理」の争いは、弁護士の仕事の中でもありふれている。
このような場合、間に立つ者(弁護士)は、いきなり「三年目」の夫の反論や11才の男子の選択の側に立つのではなく、まずは「ケアの倫理」に従い、「あなたからすればそのように見えるに違いない」と肯定した上で、少しずつ「正義の倫理」を溶かし込んでいく必要がある。若い頃の私は、「三年目」の夫の反論や11才の男子の選択の側に立っていた。「正義の倫理」に何の疑問も持っていなかった。人生の実相に接するうちに、「ケアの倫理」の方にリアリティーと親和性を感じるようになった。3年目に出た「お菊」に愛おしささえ感じている。
以上